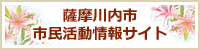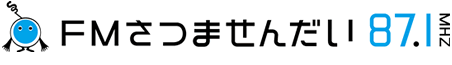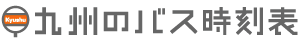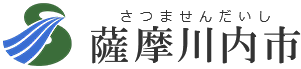このページは、薩摩川内で生活する上で、知っておいた方がよい言葉を掲載しています。気ままに更新しますので、適当におつきあいください。
○がついているのが、新登録用語です。(最新は【はんとける】です)
【秋太郎】
バショウカジキのことです。東シナ海では9月から11月が旬なのでそう呼ばれます。2022年7月21日に国際自然保護連合(IUCN)がレッドリストの3番目に指定しました。
【あたい】
会話で使う一人称。「私」を指すが、「おい」よりはへりくだって使う。
【あびき】
気象用語では「副振動」と言われるもので、特に上甑島の浦内湾で冬から春先にかけて起こる。港等を損壊する場合や浸水することもある危険な現象。瀬上地区、小島地区、桑之浦地区では要注意です。なお、同様の現象は東シナ海に面する湾内で起きやすく、奄美大島や五島列島(長崎県)でも見られる。
【甘い醤油】
鹿児島の醤油は、「甘い」です。濃い、薄いではありません。繰り返しますが「甘い」です。でもご安心を。たいていの店では、濃い口、薄口の醤油も売っていますが、基本は「甘い」です。
【いしたっ】
複数の意味があります。何かの液体が飛んできた場合や汚くなった場合に思わず発する言葉と考えましょう。主に汚くなった状態を言います。
【いっぺこっぺ】
一部始終。一から十までの意味です。
「いっぺこっぺ言ってかすっで」→「一から十まで話してやる」
【うんだもしたん】
鹿児島弁です。「これはどうしたことだ!」をとっさに言うとこれが出ます。
【おい】
会話で使う一人称。「私」を指す。
【おごじょ】
一般に女性を指しますが、かわいい女性に対して使う傾向があります。「薩摩おごじょ」は、鹿児島の女性という意味です(一説によると気の強い女性の意味がある)。
【おはん】
会話で使う二人称で、「あなた」を指す。目下に使う場合は、「わい」を使う。
【かずむ】
臭いなどを嗅ぐことを言います。良香りの場合も用います。
「この花の匂いをかずんでん」→「この花の匂いを嗅いでみて」
【かたして】
「仲間に入れてほしい」という意味です。
例:「ボクも鬼ごっこにかたして」→「ボクも鬼ごっこの仲間に入れてほしい」
【かたす】
「仲間に入れる」という意味です。
例:「鬼ごっこにかたしてやらんか」→「鬼ごっこの仲間に入れてやれよ」
【がね】
さつまいものかき揚げをイメージしていただければいい鹿児島の郷土料理なんですが、鹿児島県内でも少しずつテイストが異なるようです。名前の「がね」は、鹿児島弁の「かに(蟹)」のことで、できあがりが「かに」の姿に似ているところからきています・・・んが、薩摩川内の「がね」は衣の米粉を大量に使い、通常の「がね」よりモチッとした感覚で、由来の「かに」って何?な仕上がりです。お好みでニンジンやらゴボウをブレンドします。まっ、美味ければいいんです。
【がめっ】
がめる=盗むことです。「がめっちょったど」→「盗んでたよ」
【からいも】
さつまいものことです。全国的には、薩摩の国から広まったのでさつまいもと言いますが、鹿児島では唐(中国)から渡来したのでこのように呼びます。
【からいも標準語】
なんてことはない鹿児島弁のことです。飲み会でメートルの上がったご年配が鹿児島弁を使い理解されなかったときに、「はんなからいも標準語が分からんとか?(おまえは鹿児島弁が分からないのか?)」と使うことが多い・・・・・ように思うのは私だけ?
【からう】
「背負う」ことを言います。
「小学生はランドセルをからって学校へ行く」→「小学生はランドセルを背負って学校へ行く」
【がられる】
叱られることを言います。
【がる】
叱ることを言います。
【がんたれ】
どうしようもないヒト・モノを言います。
例「あいつはがんたれやっでや」=「あいつはどうしようもない奴だ」
【ぎったバンド】
「ぎった」とはゴムのことです。「バンド」は活塞する物。ということで、ゴムで活塞する物なので、「輪ゴム」のことを言います。
【きばる】
「頑張る」という意味です。
例「きばいやんせ」→「頑張ってください」
【きびる】
結ぶことを言います。
例「紐できびる」=「紐で結ぶ」
【きんごきんごする】
きれいにする、ぴかぴかにするという意味。対象物をきれいにすることを言う場合が多いと思われる。
例「車をきんごきんごした」=「車をきれいに磨いた」
【ぐらしい・ぐらしか】
「可哀想」という意味です。「あげなことがあって、ぐらしか」は「あんなことがあって、可哀想」となります。
【くらわす】
殴る。打つ。という意味です。
例:「頭にきたでくらわしてやった」→「頭にきたので殴った」
【こしきしま? こしきじま?】
どっちなんでしょうか?市は「こしきしま」で統一するようですが、甑島の住民の意見を聞くことなく決めたようで、市議会で揉めたようです。でもユネスコの無形文化遺産保護条約への提案書では、「こしきじま」になっているのよね~。これは2018年の拡張認定でも変わっていません。
ちなみに私は「こしきじま」の方が言いやすいので「こしきじま」と言っています。
【げんない】
恥ずかしいという意味です。例:こげなことしてげんなか。=こんなことして恥ずかしい。
【こ~むい~ん】
公務員のことなんですが、イントネーションが重要です。テレビCMで広まったのですが、「将来の何になるの~?」という問いに「こ~むい~ん」と答えるところから来ています。本当に公務員を目指しているかどうかは別として、多くの鹿児島県人は、「将来何になるのぉ~」(イントネーションに注意)と聞かれると「こ~むい~ん」と答えます。
【ゴールド集落】
平均年齢が満65歳以上の自治会のことを言う。限界集落とほぼほぼイコールだが、お年寄りの知恵は大切な宝と言うことで、平均年齢は高くても光り輝く地域という意味でゴールド集落と言うのだが、自治会が単位となっているので、中心市街地にもゴールド集落があるのは愛嬌です。。
【~ごわす】
「~です」の丁寧語・・・なんですが、冗談でしか使わず、日常で使うことはありません。外国人が、「日本に忍者がいる」や「日本にちょんまげ侍がいる」と同じぐらい勘違いされています。
【さだ】、【さだっ】、【さだくろ】、【さだくろさん】
いずれも夕立のことを言う。毎年8月16日は川内川花火大会だが、狙い撃ちしたかのようにさだくろさんはやってくる。でも開始時間には止んでいることが多い。
【ざっ ぺらっ】
「ざっとした」や「いい加減な」という意味の会話言葉です。
例「そのテストは、ざっぺらっでよか」=「そのテストは、いい加減でいい」
【さるく】
歩くというよりは、歩いて行っているが近いニュアンス。「あん人はさるっちょったど」は、「あの人は歩いていったよ」みたいな。
【じご、じごんす、じごバット】
「じご」とは、お尻のことを言います。さらに「じごんす」とはお尻の穴のことを言います。もっと言うと「じごバット」とは、ソフトボールや野球でミスしたりして愛情を込めてバットでお尻を叩くことを「じごバット」と言います。。。強く打たないでね。
【じだ】
地面のことを言います。
【じっぎょまん】
これは実際の発音を聞かないとニュアンスが伝わらないのですが、現在のれいめい高校は、名称変更前は、「川内実業高校」という男子校でした(1980年夏の甲子園鹿児島県代表という歴史あり)。それで、「じっぎょまん」とは、川内実業の生徒もしくはその卒業生を指して言います。ちなみに現在のれいめい高校は、男女共学です。
【「市内に行ってくる」】
この場合の「市内」とは、鹿児島市の中心市街地を指す。
したがって「市内に行ったついでに山形屋に行ってきた」という場合の山形屋は、川内山形屋ではなく鹿児島の山形屋を指す。
【しなびっ】
「ふやけている」という意味です。「水の中に入れちょったで、しなびってしまった」というように使います。
【島立ち】
甑島には高校がない。そのため、甑島の中学生が全日制の高等学校に進学する時は、甑島を離れなければならない。これを島立ちと言い、甑島から島立ちするまで、そしてそれからもその子のことを想うのが甑スピリッツ。それだけに子どもに対する愛情は深い。
ちなみにインターネットを利用した単位制の高校を利用するという方法がある。
学校法人角川ドワンゴ学園のN高等学校や学校法人鹿島学園の鹿島学園高等学校であれば島立ちの必要はなく、年数日のスクーリングで済む。もし島立ちをしないという選択をするのであれば、これらの高等学校を選ぶことも可能。もちろん、自分の進路は自分で決めよう。
【しゃいもで】
「どうしても」という意味です。
例:「しゃいもで参加したかっていうんなら止めんど」
「どうしても参加したいっていうのなら止めないよ」
【じゃっど】
「その通り」という意味。強調する時は、「じゃっど、じゃっど」と繰り返す。
【じゃっどん・じゃっどんからん】
「でも」、「でもね」という意味。「じゃっどん、手作業した方が早か」は、「でもね、手作業した方が早い」となります。
【じゃんか】
「違う」という意味。強調する時は、「じゃんか、じゃんか」と繰り返す。
【商工】
この場合、川内商工高校を指します。
【すったいだれる】
「すっかり疲れる」という意味です。「あんやちゃ、すったいだれちょっでや」=「あいつは本当に疲れている」という使い方をします。
【すんくじら】
隅っこのことで、クジラはいません。
【ずんだれ】
「だらしない」という意味です。
【ずんばい】
「たくさん」という意味です。強調する時は、「ずんばぁ~い」になります。
「米は「ずんばい」あっど~」→「米はたくさんあるよ~」
【せからし】
「うるさい」という意味です。
【~せん】、【~だせん】
「~です。」「~ですよね。」という意味。
例「今日はぬっかせん」=「今日はあついですね」
「今日は昼食はやっぱり「うどん」だせん」=「今日の昼食はやっぱり「うどん」だよね」
・・・みたいな。ちなみにこの「~せん」は鹿児島弁ではなく、川内でのみ使われるので、鹿児島県の他市町村で「~だせん」と言うと「お前は川内の人か」と言われます。というかバレます。
【せんこう(川高)】
ヤンキーが教師を指して言う言葉ではありません。川内高校(せんだいこうこう)の略称です。みんながあまりに「せんこう、せんこう」と言うものだから、不良が多いと思った転任してきた教師がいるとかいないとか・・・。
【川内川あらし】
川内川は九州で2番目の長さがある川。特に冬から春先にかけて、中心市街地を含む川内川流域の盆地では霧が発生し、かなり視界が悪い。中心市街地は川内平野と「平野」となっているが、盆地に限りなく近く、中心市街地から川内川河口までは川内川が山の谷間になっている。そのため、川の流れに沿って霧が河口に流れる様子が見られる。この霧が河口に向かって流れる様子を「川内川あらし」と呼んでいる。絶好のポイントは、水引町の月屋山と言われている。詳細は川内川あらしを紹介するページをご覧ください(動画もあります)。
【川内山形屋】
北薩地域唯一のデパート。「山形屋」とだけ言うこともある。ただし「市内の山形屋」と言う場合は、鹿児島にある山形屋を指すから注意しよう。
【せんで】
鹿児島県人は、「川内(せんだい)」を、「せんで」と言い、奥州仙台と区別しています。
【せんでガラッパ】
大きな川がある町には、たいていあるカッパ伝説。九州でも2番目の長さを誇る川内川にもカッパ伝説があり、川内の人のことを「せんでガラッパ」と言うことがある。
いい意味で「みんな協力しあう人たち」なのだが、悪い意味では「足の引っ張り合いをする人たち」となる。どっちの意味かは文脈で判断しよう。
【だからよ!】
「そうなのよ!」という意味ですが、あまりいい雰囲気では使われない気がする。いや、いい雰囲気の時も使うことがあるが、今まで聞いた中では肯定的なニュアンスは少ないなぁ。
A:「この間、あんたがつきあっているBさんが別の異性とデートしてたんだけど、大丈夫?」
C:「だからよ!」(「そうなのよ!いまそれで揉めてるの!」まで含む。雰囲気で悟ろう)
ちなみにこの「だからよ!」を標準語だと思っている鹿児島県人は意外と多い。
【だっきしょ】
落花生のことです。「落」→だっ、「花」→き、「生」→しょ。なのか?
【だれやめ・だいやめ】
「晩酌」のことです。店舗によっては、「だれやめセット」という焼酎+定食のセットメニューがあります。
【ちんこだんご】
「ある意味」川内名物。川内以外では「しんこだんご」と言う。見た目はみたらし団子のようだが、醤油味でほどよい焼き加減でうまい。歴とした郷土食なので、公共放送でも堂々と言える。残念なことにお土産には向かないので、食べに来るのがベストでしょう。お土産にする場合は、チンしてから食べましょう。
【ちんか、ちんたか】
「冷たい」または「寒い」という意味。
例「今日はちんたか」=「今日は寒い」
「こん水はちんたか」=「この水は冷たい」
【つぐろじん】
青あざのことです。
【ツン】
人ではなく、「犬」です。
と言っても何のことやらですが、上野公園にある西郷隆盛の銅像の横に鎮座する犬が「ツン」という名の薩摩犬です。
この「ツン」は、薩摩川内市東郷町藤川出身で、いたく気に入った西郷隆盛が所有者から譲り受けたとのこと。でも藤川が恋しかったんでしょうね。2度、脱走して藤川に帰ってきたとか。
人情に厚く多くの人から慕われた西郷さんも「ツン」に受け入れてもらうことには苦労したようです。
【てげ】
「大体」という意味合いが多い。「てげな」と同じく「とても」の意味で使うこともある。
例「てげで良かが」=「大体でいいよ」
または、「てげな」と同じく「とても」を意味することがあるので、文脈を読む必要がある言葉のひとつ。
【てげてげ】
「いい加減」の意味。通常の「いい加減」と同じで「手抜き」だったり「適度な」だったりするので、文脈を読む必要がある。
例「そん資料はてげてげでよかたいが」=「その資料は適当に作ればいいんだよ」
【てげな】
「とても」の意味。「てげなか」と言う場合がある。
例「てげなでかか」=「とても大きい」
【ですです】
会話相手にかける死の魔法デスの強化版です・・・・・うそです。
会話相手に「そうです」と応答する際に強調するときに思わず出てきます。「で」に力を入れて発音します。
「A案よりもB案がいいということですか?」「ですです(そうです、そうです)」
より強力な魔法は、「ですですぅ~」と語尾が伸び~るため、県外の人たちにはふざけているようにしか聞こえません。より強く同調しているという意味なので、激しく同意していると解釈しましょう。
【どこずいでん】
「どこままででも」という意味です。「どこずいでんついて行く」みたいに使います。
【とぼれん】
「理解が悪い」という意味です。
例「あんやちゃ、とぼれんでなぁ」→「あいつは、頭悪いからなぁ」
【鳥刺し】
九州南部では、鳥(鶏)の刺身を食します。ニンニクもしくはおろし生姜をつけて食べます。ちなみに店で出したり、料理屋で出される場合は、鹿児島県の基準を守る必要があるので、基本的に当たることはありません。
【とろいとろい】
「うろつくさま」もしくは「慌てるさま」ですが、後者の方が多いようです。
例:「あんやちゃ、水をひっちゃけてとろいとろいしちょど」
→「あいつは、水をごぼして慌てているよ」
【ないしちょっと】
「何しているの?」という意味です。むか~し、むかし、その昔。ゴルフをしている英国人に薩摩藩士が「ないしちょっと?」と言ったところ、「サンキュー」と言われたとか。「ナイスショット」と勘違いされたそうです。そう発音もそんな感じです。
【なおす】
西日本を中心にですが、「片づける」という意味です。
【なご】
「長く」という意味です。「あの作業は、なごかかっでや」=「あの作業は、長くかかる」
【なんかかる】
「もたれる」、「よりかかる」の意味です。
例:椅子になんかかる=椅子にもたれる。木になんかかる=木によりかかる。
【なんとんしれん】
「なんともしれない」の意味ですが、あまりいい意味には使いません。
【ぬっか】
「暑い」または「熱い」という意味。
例「今日はぬっかせん」=「今日はあついですね」
「こん焼酎はぬっか」=「この焼酎は熱い」
(お湯割りでお湯が多すぎる場合ですが、これは「熱い」という意味と「アルコールが薄い」という二つの意味があることに注意だ!)
【ねぶいかぶって】
「居眠りをする」という意味が主流ですが、たまに会話中であやふやな発言をしたときに、「ねぶいかぶって話をしちょ」=「いいかげんな話をしている」ということもあります。
【~のし】
「~の人たち」という意味です。「向田んしは、」は「向田の人たちは、」となります。「の」がない場合もあります。「やっしょんし」は、「役所の人たち」となります。
【はいっちょっ】
「入っている」という意味です。「コップに水がはいちょっ」みたいに使います。
【はがいか】
「歯がゆい」という意味です。
「ネジが回らんで羽交いか」→「ネジが回らなくて歯がゆい」
【はめつけて】
「一生懸命」という意味です。「あやはめつけて仕事すっでや」=「あの人は一生懸命仕事をする」。「はまって」ということもあります。
【腹かく】
腹が立つ。怒っている。という意味です。
○【はんとける】
「転ぶ」という意味です。
【ひっかぶい】
弱虫のことを言います。自分のことではなく、相手を見下して使う言葉ですが、奮い立たせるためにわざと使うこともあります。
【ひっかぶる】
水がかかることをいいます。基本は水ですが、液体全般に使います。「ペンキをひっかぶる」みたいな。
【ひったまがった】
「びっくりした」という意味です。
【ひっちゃかす】
水などをこぼすことを言います。
【びんた】
「頭」のことです。「びんたが痛か」は、「頭が痛い」となります。
【ぶえん】
鮮魚のことです。「無塩」が「ぶえん」になりました。塩をかけていない魚ですね。
【ぶんと】
「まったく」という意味です。
例「あんやちゃ、ぶんとへやっでや」→「あいつは、まったく使えない奴だ」
【へ】
二つの意味があります。ひとつは全国共通で「屁(おなら)」です。もうひとつは「灰」です。「灰」は、特に桜島の灰を指すことが多いです(もちろん燃えかすの灰を指すこともあります)。「屁」なのか「灰」なのかは、文脈で判断しましょう。
例:「へがひっと出た」→「おならが出た」
例:「桜島んへが降ってきた」→「桜島の灰が降ってきた」
【へっ】
肩甲骨あたりの筋肉を言います。肩こりの意味もあります。
例:「へっが痛か」→「肩こりで痛い」
【ほがない、ほのない】
「役に立たない」という意味です。「無頓着」という意味もあります。
【ぼやしか】
「ぼうっとしている」という意味です。
【ほんに、ほんなこて】
「とても」や「本当に」の意味です。「まっこて・まっこち」の類義語ですが、「まっこて・まっこち」の方が強めです。
「あんやちゃ「ほんに」ほがなかでや」→「あいつは本当に役に立たないな」
【まぎる】
「曲がる」という意味です。
例:「あそこをまぎっていっきやっど」→「あそこを曲がってすぐだよ」
【まっこて・まっこち】
「本当に」を強調する言葉です。おおむね好意的に捉えるといいのですが、卑下することもあるので気をつけよう。
【まっちゃん】
人名ではありません。「待ってください」という意味です。少々丁寧な言葉です。
【やっせん】
「役に立たない」という意味です。
【山形屋】
通常は北薩地域唯一の百貨店である「川内山形屋」を言う。ただし、「市内の山形屋」と言う場合は、鹿児島の山形屋のことなので注意しよう。ちなみに読みは「やまかたや」であって「やまがたや」ではない。
【よかにせ】
かっこいい男性のことを言います。どうやら私は「よかにせ」ではないらしい。
【よくろた】
「酔っ払った」という意味です。
【よんごひんご】
ねじれている状態あるいはゆがんでいる状態をさす言葉。電気コードがねじれているときなんかは「そんコードは、よんごひんごしちょっ」と言ったりします。
【ラーフル】
黒板消しのことです。
【わい】
会話で使用する二人称。あなたという意味より目下の人間に向かって使う「お前」に近いニュアンス。
【わが】
「私の」という意味です。「わがえ」は、「私の家」です。