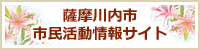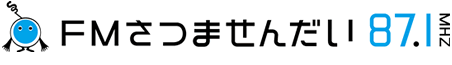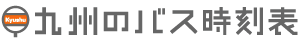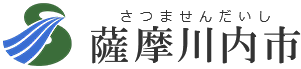○宇沢弘文(2000)『社会的共通資本』岩波新書
【中級。制度学派に肉付けをしているような感じだが、新書のレベルではない】
「広い意味での環境を意味する」ってなっているのでここにしましたが、well-beingがなじむような気もします。読み応えがあるのは、第1章。あとは各論になるんですが、それぞれの各論で社会的共通資本の説明が出てきたり、歴史が出てきたりするので、読みにくい印象です。でもそれにはきちんと意味があるので、耐えて読むことになります。んが、内容が膨大なだけに新書では納まっていないと思いました。
特に経済学的な観点で読んでいる私には少々物足りない感じがしました。
また、少し古い内容になるのも気になってしまいました。歴史観になってしまいました。この辺は若い学者が議論を深めてほしいと思いました。基本的にリベラル思考なので肌には合いました。
(2025/07/30)
○浜本光紹(2024)『新・環境経済学入門講義』創成社
【初級。ミクロ経済学の基礎がなくても読める本です】
タイトル通り環境経済学の基礎が学べる本です。基本は新古典派経済学の理論に基づいて解説がなされており、ミクロ理論の壁を乗り越えていないのでこれから環境の経済学を学びたいと思った時に読むといい本です。そこからテーマを決めて研究をするといいでしょう。
直接規制についても言及され、排出権取引も掲載されています。繰り返しですが、初学者にちょうどいい本だと思いました。(2025/06/05)
○ウィリアム・ノードハウス著 江口泰子訳(2023)『グリーン経済学』みすず書房
【初級。環境の経済学を学ぼうと思って割と早いうちに読んでおくとよい】
環境の経済学に関連してノーベル経済学賞を受賞した著者による著書。ミクロ経済学で外部経済のことを理解した上で読むとよいでしょう。
タイトルに「経済学」とついていますが、面倒な数式は出てこず、現在では専門化が進んでいる環境問題の諸課題をさらっと叙述しています。なので、本書を読んでより極めたいと思ったらその箇所を読み込んで、専門書を読むためのものと考えてください。
本書は「経済学」となっていますが、政治や倫理、思想についても触れています。私なら「政治経済学」というタイトルにしたと思います。まぁ、著者が経済学って言っているのでいいのでしょうが。(2025/01/30)
○大沼あゆみ・柘植隆宏(2021)『環境経済学の第一歩』有斐閣ストゥディア
【初級。主流派経済学のテキストで読みやすい】
主流派経済学の分析手法について解説していますが、必要最低限のミクロ経済学も説明されているので、環境経済学を学ぶ前に手にしていい本だと思いました。本書では、環境問題は経済問題であるということから始まります。まぁ、これにはいろいろご意見あるでしょうが。ここで言う「環境」は「自然環境」とも言い換えられています。ここは注意点です。
環境問題について、経済学の手法について説明していますが、どうでしょうか?水俣病は解決した環境問題でしょうか?解決していないと思う方は、さらに環境経済学もしくは環境経済論について研究してみるといいでしょう。(2024/04/07)